累計販売数、社会的影響力ともにインディーゲームとして大きなインパクトを残した『NEEDY GIRL OVERDOSE』。本作は、承認欲求とインターネットの闇を抱えた少女「超てんちゃん」をアシストする「P(ピ)」となり、彼女を最強の配信者に育て上げる育成シミュレーション要素をもつアドベンチャーゲームだ。
オーバードーズやリストカット、性描写といった過激な描写が特徴の本作だが、承認欲求、薬物、愛など、それらを「脳内快楽物質(報酬系)」への依存として描き出し、アルゴリズムや他者に干渉され続ける現代において、環境そのものの病理を浮き彫りにしたことは明白だ。
そんな本作がアニメ化され、2026年4月にTV放送を開始する。 このアニメ版では原作者・にゃるら氏自らが新しいキャラクターや新しい視点とともに全13話の脚本を執筆し、物語を再構築している。ゲームがマルチエンディング形式であることを踏まえると、断片的なゲームの物語をただ単に描きなおすことは難しい。ゲームと同様に鋭いメッセージが込められた野心作であることが伺えるだろう。
今回はアニメ制作の裏側だけでなく、「エロゲ文化」への眼差し、そして現代の若者が抱える孤独と「表現の自由」まで、企画・監修・脚本のにゃるら氏、アニメ版プロデューサーであるYostar Picturesの稲垣亮祐氏のインタビューをお届けする。
聞き手:福山幸司

「好きにやっていい」。商業アニメの常識を覆す全話脚本への挑戦
――アニメについて詳しく聞く前に、ゲームにおける、にゃるらさんの原体験、つまり物語性のゲームの原体験を聞いてみたいと思いまして。最初に物語性を意識したゲームは何だったんでしょうか?
にゃるら:
気づいたときにはギャルゲーをやっていたので……ただ、ゲームシステム以前に物語性を意識したのは『ドラゴンクエストVI 幻の大地』かもしれないですね。
僕は世代的には『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』なんですけど、幼稚園か小1ぐらいのころだったかな。母がミーハーだったから『ドラクエ』を買ってきてプレイしました。ただ、『VII』はさすがに幼少期で最初だから意味が分かんなくて。ただスーパーファミコンもあって、今度は『VI』やってみたら、面白かったという記憶があります
――それは意外なタイトルですね。『ドラゴンクエストVI』の物語に琴線が触れたということでしょうか?
にゃるら:
そうですね。子供だから「夢」と「現実」が二つの世界として分かれていて、交差するストーリーすげえと思いましたね。しかも主人公のほうが夢だったみたいな。あと伏線の張りかたとかは、物語を作るうえでも結構学んだような気がします。
――実はこちらの事前に準備した質問案でも『ドラゴンクエストVI』を入れていました(笑)。のちほど関連したテーマに触れますね。
にゃるら:
本当ですか。すごい、ピンポイントすぎる。
――さて、にゃるらさんは今回、企画・監修だけでなく脚本も手がけておられますね。原作はマルチエンディングですべてを「描き切った」ようにも見えますが、まだ描くべきものが残っていたのでしょうか?
にゃるら:
描きたいものが「見つかった」というのが、近いかもしれないですね。確かにおっしゃるように、ゲーム内でやったことは全部やったつもりです。
だからアニメ版でゲームでやれなかったことを補足する感覚は一切ないです。ただ、稲垣さんと協力体制ができたなか、ある意味、色んな雑務などをパスしても大丈夫なのであれば「一から新しいことに挑戦しよう」という気持ちで挑みました。
――稲垣さんにはアニメ版を最初どういう相談をされたんですか? そもそもどちらからお話があったんでしょう。
稲垣:
僕と『NEEDY GIRL OVERDOSE』との出会いは、うちの会社のイラストレーターが「これ絶対、稲垣さんが好きなやつですよ」と、発売前に教えてくれたんです。その人は、ゲーム内のイラストも描くことになる人でもあって、のちににゃるらさんを知るきっかけになった人なんですが。
実は僕、元々はゲームを作りたくてこの業界に入ったんですよ。専門学校を卒業してたまたま入ったのがアニメ会社で、そこから20年以上アニメ一筋でやってきましたけど、やっぱりゲームへの憧れはずっとあって。 「今なら個人でも作れるんじゃないか」と思ったり、VRの専門学校に通ってVTuberを作ろうとしたりもしていたんです。
――稲垣さんはどちらかというと、ゲームを作りたいと思っていたほうなんですか?
稲垣:
もともと専門学校時代からゲームを作りたいと思っていて。そういう意味では、にゃるらさんと趣味が結構合ってて、プレイステーション、セガサターン、PCゲームとかやってましたから。それこそアリスソフトの『鬼畜王ランス』とか、あの世代のゲームを学生時代にプレイしていたり。
――なるほど、そこがにゃるらさんと共通言語だったんですね。
稲垣:
そうなんですよ。僕は『VA-11 Hall-A』みたいなゲームが好きだったんですけど、自分もそういうゲームを作りたいなと思っていて……もちろん自分ですべてをイチから作ろうとまでは思っていなかったですけどね。でも、大体どういうふうに作るかというのは、ちょっと想像はできる。僕自身、スクウェア・エニックスにいた時期もあって、知り合いをたどれば作れるんじゃないかと。
そんななか個人の制作会社として「albacrow」を起業して、しかもゲームも作ってみたいと思っていたタイミングで、実際に僕が作りたいようなゲームを体現して、しかもヒットさせているにゃるらさんと偶然知り合えた、という感じです。
にゃるら:
本当に偶然でしたよね。あとは単純に住所が近かったのも大きいですね。Yostar Picturesが中野にあって、自分も中野住みなので、気軽に歩いて10分ぐらいで遊びに行ける。そういう意味でも本当に気が合いました。
――Yostar Picturesによるアニメの制作が進んでいる中で、映像をご覧になった感触はいかがですか?
にゃるら:
現時点で、横で見ながら感動していて、「早く公開してみんなに見てもらいたい」と思ってます。超てんちゃんの声と台詞もイメージ通りで、 超てんちゃんが完全に超てんちゃんです。
ただ8割ぐらいキャラクターがしゃべってるぐらいのアニメなので、「常に誰かが長文をしゃべってて怖いな……」というのが僕の率直な感想ですね。キャラクターが黙っているときがない。
稲垣:
ディティール含めて、すごく見やすくなっていると思いますよ。「普通は言わないこと」と「普通はしないこと」をアニメで描いています。
にゃるら:
本当にありがたいことです。なにしろ本当にキャラクターがずっとしゃべっちゃうから。それぐらい台詞が本当に多いんですよ。自分が毎日、テキストを書いてるから、脚本も必然的に言葉が多くなっちゃって。ゲームのときはテンポを損なわないようにどんどん文字を切ってたんですけどね。
――にゃるらさんが、13話分の脚本を書かれたんですよね
稲垣:
その通りです。『新世紀エヴァンゲリオン』が庵野秀明さんしか作れない作品だったのと同じように、アニメの『NEEDY GIRL OVERDOSE』のほうも、ゲームと同じくにゃるらさんしか作れない作品になっています。
にゃるら:
僕としては、アニメで本当にやりたいことやらせてくれるんだったら、何も文句を言わずにとにかく「全部やろう」と思いました。ただ、アニメ作りはこういうものかと思ってて、途中までそれが結構、特殊なことだということに気づかなかったんですよね。
後から言われて気づいたんですけど、「本当に好きにやっていいよ」と言われたときに、本当に好き勝手に13本を書くやつがどれだけいるのかという。
稲垣:
そうそう。僕の周りのクリエイターでも、本当に好きにやってもいいという環境を与えても、やりきれない人がほとんどです。1、2本ぐらい出して、ちょっともうモチベーションが……みたいな人を結構見てきているなか、ちゃんと13本の脚本をすごい勢いで出し切っていただいたのは、単純に尊敬しました。
――しかし稲垣さんから、にゃるらさんに何か注文とかはなかったんですか?
稲垣:
これはアニプレックスのプロデューサーも含めてですが、「にゃるらさんがやりたいことを全部出してくれ」、「すべてを出し切ってくれ」と。
にゃるらさんはアニメ脚本の初挑戦だったので、1話の尺感とか、何文字詰めで何ページぐらいで20分のアニメになる、とかは教えませんでした。もちろん話数によっては内容が足りないとか、そういうのもありましたが、そのあたりは全部、監督の中島政興が調整してくれて。最初からゲームの内容だけだとアニメシリーズ13本は無理だろうとは思っていたので、中島のほうで13本分の尺感に揃えています。
メーカーや原作者の方から「有名な監督を連れてきてほしい」、「有名なキャラクターデザイナーにお願いしたい」、「有名な脚本家にお願いしたい」という話が他のアニメだと出ると思うんですけど、全員がにゃるらさんのこと理解できるかというと時間もかかるし、やってみてうまくいかないこともよくある話だと思うんですね。
――確かに有名な監督だと、そちらの方の主張が強く出ますね。
稲垣:
有名な監督を起用してしまうと、にゃるらさんがやりたいことと違ってくる可能性があるじゃないですか。それに、にゃるらさんの生き方や人生観に共感できる人じゃないと一緒に仕事するのは難しい。アニプレックスさんや、にゃるらさんにも「有名なこの人が好きだから連れてきて」とは言わないでくれと、最初からお伝えしていました。
僕が知っているなかで、にゃるらさんをちゃんと立てて、それを形にしようと真面目に取り組んでくれる人は、社内の中島だと思ったので彼に監督を任せました。「『NEEDY GIRL OVERDOSE』好きなんだ、ショートアニメをしてくれ」と言い、それを実現した中島のことを信頼して、彼が作れる体制を作ろうと僕としては意識して会社のみんなにお願いしました。
――にゃるらさんを100%出せるような作品を作ろう、ということですね。
稲垣:
そうですね。一時、にゃるらさんの脚本が全部上がりきったあとぐらいに、全話のアニメのコンテ作業に入れるようシリーズ構成を組み替えていた段階では、中島も「俺が今現在、現時点でにゃるらさんの頭の中を一番理解できている」とはっきり言えるぐらい頑張ってくれましたね。
――にゃるらさんは、13話分のシナリオはどういうふうに作られたんですか? プロットから考えるのか、それともキャラクター先行なのか。
にゃるら:
今回、新キャラ出そうというのが先にありました。その人たちと超てんちゃんがいたときにどうするのかというのを逆算して、13話分広げるみたいなことをやりましたね。
もちろんそのほかにも「やりたい要素」みたいなのはいくつかあって、漫画『コブラ』の作者の寺沢武一が、「自分がやりたい、かっこいいシーンが頭にあって、それを無理やりストーリー繋げて作る」と言っているですけど、それに近いかもしれないです。
――シーンありきで、みたいな。
にゃるら:
そうですね。シーンとキャラを無理やり整合性つけて13話分繋げていった感覚が近いです。それを許してもらえたのが、僕にとっては本当に奇跡でした。
――すごいですね。
にゃるら:
ええ、やっぱり一緒にやる人の好みに合わせた方が、一番効果が出ると思うんで。二人三脚で作ってるようなイメージあります。お久しぶりさんのデザインは絶対に活かすべきだと思ってましたので、そういう意味ではお久しぶりさんも「ぴったりの声優の方が見つかった」と、本当に喜んでました。
――その3人の新キャラクターは配信者で、超てんちゃんと競い合っているという感じなんですか?
にゃるら:
配信もしてます。
稲垣:
『カラマーゾフの兄弟』のあたりはネタバレになるから言わないほうがいいかもしれない(笑)。
にゃるら:
ちょっとは明かしてもいいと思いますよ。
僕のなかで『カラマーゾフの兄弟』の3人兄弟が、それぞれ何を表してんのかなと考えると、それは「真・善・美」なのかなと思いまして、それを今回、それぞれのキャラクターたちに振り分けてます。「真」と「善」と「美」に関して、それぞれのキャラクターが、それぞれの主張を喋ってるようなイメージです。
――「美」というのは、この場合、快楽主義的なイメージですか?
にゃるら:
いや美術的とか、美意識とかですね。
――なるほど。しかし「真」というと……?
にゃるら:
いやまさに、「真」が一番難しかったですね。「善」と「美」は雰囲気やニュアンスで分かるんですけど。「真」というのが何なのかなというのは僕も脚本書きながらずっと考えました。
台詞が多いというのも、「真・善・美」についてキャラクターたちが議論ばかりしているからなんですよ。議論しかしてない回が2回ぐらいありますからね。ずっと喋ってるから絵的にどうやって持たせようと悩んだ回がいっぱいありますから。
――そこは映像的には、ずっとカットバックしてるという感じなんですか?
にゃるら:
ええ、もう監督の力を借りて演出してます。まあ突然、花とかを挿入したりして、とにかく画面が賑やかで飽きさせないようにしようというのはいろんなアイデアを出しました。
――にゃるらさんはnoteで、ジャン=リュック・ゴダールの映画『中国女』に触れられてましたけど、お話を聞いてると、そういうポップな感じで、やられてるのかな?と思いました
にゃるら:
監督の中島さんも実写映画が好きな方だし、稲垣さんもハイクオリティな作画で殴るというよりは、予算じゃないところの勝負だと考えている人で。それこそゴダールのヌーヴェルバーグの低予算的映画的な作り方ですね。
特にゴダールの映画から演出として使ったのは、絵的に激しい場面だけど、文字を出しちゃっていいみたいな。文字だけで画面埋めていいから、その方が早いというのははやっちゃいましたね。本当に絵コンテ見た時に「この方が早いわ」と確信を持ちましたけど。あと今回の3人の新キャラクターたちは、現代の若者として感情移入できるような視点として用意しています。

――今回のポスタービジュアルで、スタンリー・キューブリックの映画『時計じかけのオレンジ』がオマージュされていますが、そういった「若者」みたいな文脈なんでしょうか。
にゃるら:
キューブリックの『時計じかけのオレンジ』は人間の暴力性を描いていますが、「なんで若者がこんなに暴力に走るのか」とか、善悪とかの話ばかりしてると思うんですよ。
『NEEDY GIRL OVERDOSE』はそれに近いものだと思ったんですよ。『時計じかけのオレンジ』は暴力というテーマに向き合いすぎたら、暴力的すぎて、理解できなかった人から叩かれて上映禁止になったわけですけど、僕としては『NEEDY GIRL OVERDOSE』も薬物とか反社会性とか何なんだろうと考えて、真摯に書いたつもりの作品なので。
アニメ版だとそうしたテーマが、顕著に出てると思うんですよね。暴力性とか……『NEEDY GIRL OVERDOSE』の場合、暴力そのものじゃなくて薬物とか快楽とかですけど。
――ゲームでも脳内の報酬系みたいなところで「薬物」とか「恋愛」とか「インターネット」がテーマとして綺麗に繋がっていますよね。これは初めからコンセプトとしてあったんですか?
にゃるら:
まあ自分の頭の中でそもそも繋がっていたことですね。人間は幸せじゃないけど「報酬系」を欲しがるわけなんで。 一番簡単に報酬系が出るのがまず薬物だろうというのが、基本的に重い薬物中毒の考えであると思うんですよ。 で、どうせ薬物まで行かなかった場合、インターネットで何かを与えたり、または何かを絶賛すれば、脳内麻薬が生まれるわけで。人間は報酬系の奴隷であることは変わんないよというのは、ずっと考えとしてはあります。
そういう意味では、ドストエフスキーやキルケゴールにやっぱり近いですね。つまり「絶望」は「人間らしいことをするからなんだ」と。暴力とか依存とか「人間だから」以外理由がないと思うんで。
――『時計じかけのオレンジ』は、後半で主人公のそうした「人間らしさ」が人体実験で矯正させられる展開になりますね。

にゃるら:
結局、社会が強制的に善人を作り出すことに意味があるのか?みたいな。しかも結局、意味なかったから元に戻るわけだし。「善」というものがどこにあるのって話で。 最終的に『時計じかけのオレンジ』の解釈は、視聴者に委ねられたわけじゃないですか。僕は『NEEDY GIRL OVERDOSE』もそうありたいと思ってますね。
――ゲームのほうで僕のなかでひとつ謎があって。すごく破滅的な「INTERNET OVERDOSE」のルートで「胡蝶の夢」に言及されてて、あれは何なのかなと。
にゃるら:
頭がおかしくなっていく過程で「夢か現実か」という部分で、僕の中で幻覚のイメージで「モルフォ蝶」というのがあったんですよ。押井守の作品とか蝶々をかなり「胡蝶の夢」と意識して使っているので、元ネタはそこからですね。
実は、超てんちゃんの裏モチーフみたいなところではあります。そもそも「あめちゃんが見た夢」としての「超てんちゃん」というニュアンスは、どのルートでも共通かもしれません。
「トー横」と「オタク」は鏡像関係にある――行き場のない寂しさの正体
――にゃるらさんの若者への感性はどうやって掴んでいるんですか?こういう文化的な歴史とは違う部分ですよね。 実際に若者と会って取材をしているとか?
にゃるら:
結果的にですけど、今、自分のツイートに英語圏からリプライが来たりするんですよ。「水飲んだ」ってツイートしたら「私も飲んだよ」みたいなのが15個ぐらい来る。僕が無意識にやってた妙な親近感というか、「この人にはこういうふうに遊んでいいんだな」というファンタジーが勝手に伝わってくるんですよ。そうなると自分も、その人たちのことなんとなく分かるなと思っちゃうんで。互いに言語化できない空気、かっこつけて文学的に言えば、同じ寂しさを背負ってんだな、みたいな。
――同じ寂しさ、ですか。
にゃるら:
日本で今、一番衝撃なのは「トー横」の問題だと思っていて。オタクたちは、元から居場所がないからインターネットにいたわけじゃないですか。なのに、現実で居場所がない「トー横」の人たちをオタクたちが叩いてる。僕、これ本当に意味のないことしてるなと思って。 お互い居場所がないからどっかで頑張って集まっている同士で、リアルとネットという一枚隔ててるだけで一緒なのに、そこで理解できないんだなというのが本当に不思議で。
寂しくてどこかで集まって、当然、疎外された人たちだから良くない文化を中心に集まってるかもしれないけど、それって「ネット」も「トー横」も同じじゃんと思います。
そういう空気が今回のアニメではできたのかもしれない。それがなんかこう……若者の救いとかに勝手になってくれるなら、もしかしたら、そうなるかもしれない……。いや僕はそんな意識してないですよ。ある意味、10年前ぐらいの自分の意識をそのまま脚本に書いてるだけのところもありますし。
稲垣:
「トー横」にいる人たちや、歌舞伎町にいる人たちと同時代にいない人間からすると、彼らがアニメキャラクターみたいにかっこよく捉えてしまう部分は、僕にもありますよね。生き方として逆にかっこいいなと。エンタメとしてそのとき、その時代のキャラクターとして描き、昇華している作品が『NEEDY GIRL OVERDOSE』だと思っているので。

――僕は今、にゃるらさんが「オタク」や「サブカルチャー」と「トー横」を接続するのはちょっと不思議な感性だと思いながら、聞いていました。
にゃるら:
僕は「メインカルチャー」と「サブカルチャー」で分けたとして、ちゃんとした大学出ているとか「メインカルチャーがうまくいってる人たちのものだ」と定義をした場合、「トー横」とかの変な文化自体がサブだから、そういう意味ではサブカルチャーだと思いますよ。むしろ「トー横」はサブカルチャーとして、ど真ん中だと思いますけどね。
稲垣:
ちゃんと普通に生きてない人たちの物語というのは、やっぱりエンターテインメントじゃないですか。北野武監督の『アウトレイジ』とかそういうのにしてみても。ちょっと極端な例ですけど。
――『池袋ウエストゲートパーク』とか……。
稲垣:
そうそうそう!そんな思いっきり暴力にもいけない、極端に悪いことできない。でも強者でもない。弱者がかっこつけている。まあとはいえ、そうはなりたくないなと思いつつ、憧れている部分もありますが。
にゃるら:
それも大事な反面教師ではありますからね。僕は『池袋ウエストゲートパーク』と今回の『NEEDY GIRL OVERDOSE』でやってることは、かなり近いと思っています。夜の街に弾かれたものが集まって、社会に馴染めないから個性を極めるしかなくて、不良だったらヤンキーファッションになり、女の子だったら今風のファッションになる。
僕は、ヤンキーとオタクとほぼ似てると思ってて、オタクもヤンキーも同じ工業高校の同じ教室にいて、仲よくしている風景を見てたんで。 ヤンキーたちは「不良」という属性に頼ってコスプレをしてて、自分じゃないものになって、かっこつけたりとか、なにひとつ変わりはないと思いますね。
稲垣:
本当にそう思いますね。僕も工業高校でオタクだったけど、ヤンキーが仲良くしてくれるんですよ。
にゃるら:
根本は一緒ですよね。寂しいから教室に居て……そこに何の違いがあるのか。趣味嗜好は違うかもしれないですよ。でも一緒に麻雀して、パチンコやって、格ゲーをやって。
僕が中学校の頃『THE KING OF FIGHTERS 2002』がすごい流行ったんですよ。ヤンキーの方がコンボが上手かったりして、オタクの方が『MELTY BLOOD』や『GUILTY GEAR』に浮気しがちだったから、弱くて、そのなかで極めるやつは極める。そこに「オタクだから」、「ヤンキー」だからとかではないと強く思いました。実際、『鉄拳』プレイヤーとかは、ちょっと柄の悪いやつが強かったり。
――「オタクとヤンキーが仲良くしている」という一方で、「仲良くしていない」という両方の空気感が僕の記憶の中にあって。僕は85年生まれで個人的にはヤンキーと仲が良かったんですが、「オタクが気持ち悪い」、「オタク的なアニメは気持ち悪い」と公言するヤンキーもけっこういたような気がして。
稲垣:
そうですね。僕も82年生まれなんで、年代的には近い方だと思うんですけど。本当にオタク文化が90年代、2000年代……今に向かって市民権を得ていく感覚はすごくわかります。
にゃるら:
そうなると僕が、小学校で00年代なんで、その頃にはやっぱり名残はあれども、工業高校に行くときにヤンキーたちはオタク文化に対し「キッショ」とは言ってなかったですね。だってパチンコ行ってエヴァを打って、「初号機かっこいい」とか「綾波可愛い」とヤンキーが言いますから。それぐらいの時代でした。
――庵野秀明さんが『Air/まごころを、君に』で、「オタクは現実に帰れ」的なメッセージを発したのも、90年代後半の過渡期的なものな気がしますね。美少女ゲームやエロゲ文化を作った蛭田昌人さんとかシュッとしてるし、『ドラゴンクエスト』の堀井雄二さんにしろ、オタク文化を形作った人は、オタクではなかったように思えるんですね。
にゃるら:
結局、旧劇のときにパソコン通信の掲示板に書かれた、誹謗中傷を引用してるわけじゃないですか。オタクが適当なこと言ってるから「現実見ろ」という、庵野さんのなかでの拒絶反応だったと思うんですけどね。
庵野さんが「オタクは現実に帰れ」的なメッセージを出したのは、僕は『NEEDY GIRL OVERDOSE』がヒットしてから、おこがましいけど、すごく気持ちわかるところあるんですよ。一回もプレイしてないし、その適当な噂で「にゃるらはこういう感じなんだろ」と叩いてるやつを見ると「一次ソースを大切にしなよ」と。今のSNS、有象無象に対してはマジでそう思いますね。
「鬼畜系」の系譜と「強者」の文学。『NEEDY GIRL OVERDOSE』が継承した「支配」の物語
――90年代のサブカルチャーの主人公の描き方が、大雑把に言えば「肉食系から草食系」に変わっているような気がしていて。最初に挙がった『ドラゴンクエストVI』はその変化の渦中にあって、たとえばその前の『同級生』は肉食系の強い主人公として、女の子をナンパしていくじゃないですか。
にゃるら:
そうですね。
――にゃるらさんも意識的にやられてますけど、90年代のエロゲやゲームを文学史に捉えなおさなきゃいけないと思ってて、近代文学は『ドン・キホーテ』以降、ドストエフスキー的な「弱者の内面」だけでなく、マルキド・ド・サドやホームズのような「強者の内面」を描く流れに分岐した気がするんですよ。本来のエロゲー文化は、実はその「強者」の系譜にあったのではないかと思うんですね。
にゃるら:
『ランス』シリーズのような、強い支配者みたいな意味ですか?
――そうですね。どこかでエロゲーが「文学」として扱われるようになったとき、「弱者の内面」の文脈が尊重され、サド的な「強者の内面」の系譜が位置づけられないまま来てしまった気がするんですよ。たとえば『学園ソドム』とか、elfの『臭作』はその筆頭ですが、elfはその後にも団鬼六の小説『花と蛇』をゲーム化したり、『河原崎家の一族2』のテキストもすごく文学的なんですよね。
にゃるら:
ああ、ありましたね。
稲垣:
(笑)。僕は『河原崎家の一族2』好きですね。
にゃるら:
『臭作』とか『学園ソドム』とかの陵辱ゲーは、良くも悪くもLeafやKeyが塗り替えたわけじゃないですか。『To Heart』が出てきて、『ONE 輝く季節』が出てきて、「学園で感動で、純愛がいいぜ」となった上で、『Kanon』と『AIR』がトドメさした。そこで「文学の時代だ」となっちゃって。
――でもどっちも文学のはずなんですよ。そういう視点で見た場合、『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、実は「強者のエロゲ文学」の流れにもあるんじゃないかとも思うんですね。
にゃるら:
エロゲの用語でいえば「鬼畜系」ですね。まさに『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、そういった「鬼畜系」の枠にあるんですよ。確かに本来の美少女ゲームはそこにあって。僕が『NEEDY GIRL OVERDOSE』のステータスのシステムは、わかりやすく『モンスターファーム2』と言ってるときがあるんですけど……実際、もう少しイメージしてたのはPILの『地獄SEEK』というか。調教ゲージのあるゲーム、鬼畜系をイメージしてたんですよね。
――なるほど、まさにサド系譜のゲームですね。
にゃるら:
「女の子を支配するぞ」みたいなガツガツした最初の原住民だったエロゲーマーというのは、90年代にだんだん隅に追いやられてたんでしょうね。
稲垣:
『カスタムメイド』がありましたよ(笑)。
――(笑)
※にゃるらシナリオでの新作ビジュアルノベルゲーム
にゃるら:
本当は主流だったけど、エロゲーの中ではサブのジャンルに鬼畜系がなっちゃったんですね。ただアニメとか映画とかの文脈でなかなかできなかったのを、電波ゲーはかなり拾ってるなと思いますね。本当に狂っているということを描くことが成立する媒体が、多分エロゲーにしかなかった。
稲垣:
『終ノ空』とか。「これで作品になるのか」みたいなようなのもちょっと表現としてはありましたもんね。
にゃるら:
まさにそうですね。結局は『終ノ空』自体が、作品として色々と片手落ちだったところを、リメイクの『素晴らしき日々 〜不連続存在〜』が大ヒットなんで、そういう意味ではあの時代は試行錯誤できたいい時代だったかもしれないですね。
――僕もアリスソフトやelfとかが好きな古い人間だから、最初はビジュアルノベルに抵抗があって、ニトロプラスの『吸血戦記ヴェドゴニア』をやったときに、なんで「アニメ文法的なOPいれるんだ、ゲームはゲームの表現を追及すべきだ」と反発してましたから。
にゃるら:
それは失礼ながら、若さゆえの怒りという感じで面白いですね(笑)。ゲームにアニメをいれてもいいじゃんと思いますから。
稲垣:
僕は逆にちょうどゲームを作ろうと思ってた時期なんで、『吸血戦記ヴェドゴニア』をやって「これでやろう」みたいな感じがして(笑)。変に選択肢をいっぱい作らなくていいじゃないですか。これで当時、「吉里吉里」でゲームを作ろうとしましたから。

――それは素晴らしいですよ。本来はそうあるべきだと思います(笑)。
にゃるら:
ただ僕もそのゲーム性というのは同じ気持ちですよ。そういう気持ちを悶々と思っていたので、『NEEDY GIRL OVERDOSE』を美少女とのコミュニケーションのゲーム性はあるべきだろと作ったわけで。そういう怒りから始まってるところはあります。僕もアリスソフトが大好きなんで。
――『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、アリスソフト的なゲーム性とか、あるいはPILとかのアングラなルーツがありつつ、そうしたメインストリーム性も取り込んでいて、ど真ん中のアングラには行かないさじ加減がありますね。
にゃるら:
いやでも、それは奇跡ですよね。僕はもっとドアングラなものとして終わると思ってた作品なんで。
今もここまで流行ったからカジュアルに消費されてるだけで、一歩世界線を間違えればドアングラな意味わかんないものとして、こじんまりしたヒットになったと思いますよ。
――もうひとつの2000年代の動きとして『NEEDY GIRL OVERDOSE』に繋がるという意味で、その裏で進行していたインターネットにおける配信者文化の台頭は、にゃるらさんはどう見ていたんですか?たとえば先駆者の永井先生とか。
にゃるら:
永井先生は知ってはいましたけど、配信を見るという感覚が僕にはあんまなかったんですよ。むしろインターネットでのヒーローが現れたとき、「チャラチャラ集まりやがってよ」みたいなちょっとアンチだった思春期でしたね。テキスト文化の人間だったんで。
でも、そこでキャラクターがキャラクターとなって前に出るということで、やっと意味がわかったんですよ。
――意味がわかった、というのは?
にゃるら:
配信というものでなりたい自分になって、欲望を満たす。「あ、そういうことか」みたいな感じで腑に落ちました。
つまり2次元という皮を被って「こういう私になりたい」、「こういう俺になりたい」というのは、すごく意味がわかったんです。 ようするにTRPGなんだ、みたいな。
――ああ、それはなんか『NEEDY GIRL OVERDOSE』の核心に触れたような気がしますね。
にゃるら:
確かに今まで言ってこなかったかもしれませんね。永井先生ぐらい、その本人とキャラクターが一致してるものは、さすがに僕としてもわかるんですよ。
ただ2次元というキャラクターが出てきて、2次元キャラクターになりたいというチャレンジャーがいて、そのとき、どれだけ2次元キャラクターに徹するんだというときに、皆が「どれどれ?」と楽しみに見に行く、この意味はわかった。
――なるほど。そのタイミングというのは、やっぱりキズナアイとかになるんですか?
にゃるら:
そのぐらいですね。確かに2次元キャラクターになりたいとみんな思ってるし、この方法でなれるし、そこに、みんなが「本当にお前を信じていいんだね」とオタクたちが集まったっていうのはすごい意味がわかりました。
2次元のキャラクターがずっと夢を見させてくれるのに、素の自分を見せるメタ的なことをたまに言う。たしかにそれもオタク好みだよねと、いろんな理解がVTuberで深まりました。
「精神疾患の消費」への回答。表現の自由とにゃるら自身のカルテ
――あえて聞くんですが、『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、その過激なテーマゆえに議論を呼ぶこともありました。たとえば、リストカットのような描写がプレイヤーに悪い影響を与えるのではないか、という懸念についてはどうお考えですか?
にゃるら:
作品としてテーマとして扱おうというものがあったとして、それが2次元に収まっている限りは、僕は作品として守られるべきだと思います。だとしたら、エロゲの絵そのものもダメなわけだし。男の願望の塊として、これまで話してきた『臭作』が登場してるんだから、そうした表現は絶対に守られるべきだと思っています。
たとえば2次元のせいでリスカをしましたと言われても、「それは2次元に思考を預けたあなたが悪いよ」としか、思わないです。正直、その人の後の人生のどこかでしていただろうと思いますし。そういう経験を踏まえたうえで、リスカというものになぜハマるかハマらないかとかいろんなこと考えればいいので。「そこで怒られてもな」とは思います。「それはあなたの人生経験だよ」としか思わない。そこはもう絶対譲らないですね。
――ただ、僕のなかで人はけっこう弱くて、脆い部分もあるとあるんですよ。表現の自由は守られるべきですけど、宣伝とか文脈がない程度では、やはりゾーニングに近いものがあるべきじゃないかという意見もわかるんですよ。
にゃるら:
確かにインターネットがゾーニングできなさすぎる問題があるので。ただ、ゾーニングされすぎた場所でやっても広がらないジレンマもあるので、それはありえない前提になっちゃいますよね。
――以前、IGN Japanに掲載された池田伸次さんの記事で「『NEEDY GIRL OVERDOSE』は精神疾患がカジュアルに消費されている。精神疾患の専門家が監修した作品にも注目して欲しい」という論評がありました。あれについてはどう感じましたか?
にゃるら:
精神病の女の子を見世物にするかどうかという話だとしたら、僕自身もいろんな精神とか身体に問題があって薬物中毒で活動してたなか、それを武器に戦う女の子っていうのを描いたわけだから、「そこを批判されてもなぁ」とはちょっと思いましたけどね。「見世物にしちゃいけないよ」というのを逆に破って、「私はこんな女の子だけど生きてるぞ」と主張して描いたのが、超てんちゃんなんだから。「そういう子がいたら悪いのか?」という話だと僕は思います。若い方に『NEEDY GIRL OVERDOSE』を支持してくれいる人が多いのは、そういうところだと思っています。
――なるほど。あの記事は池田なりに誠実に書かれていて、ひとつの意見としては僕はありだと思っています。
にゃるら:
「私は精神病の女の子で、鬱病です、うまく生きられません」で終わるよりは、「私はこんな女の子だぞ」と戦う姿を描いたわけなんで。「見世物にしちゃいけません」というより、本人が見世物になっても強く生きようという姿の作品なんで。
――もちろん作品では文脈があるので表現の自由は守るべきだと思います。 ただ文脈がないところ、特に「宣伝で気をつけてほしい」という感じですね。
にゃるら:
宣伝の部分はたしかに同意です。宣伝でセンセーショナルに人を傷つけていいかという話だとしたら、それは確かに違うと思います。ただ作品は何があっても守られるべきものだと思います。
僕は、「人が人でいてほしい」といくだけの話なんで。インターネットの意見というものに呑まれて、もうネットと同じことを喋ってるだけという人が多すぎたときにね。たとえば僕が20代前半でやらかしたこととか失言したこととかいっぱいあるんですけど、今、30になった自分から見たら「まあこれでも人間だから」としか思わなくなって。
他の人のやらかしとかを見ても、「まあ人間だから」としか思わないから、そこはネットの流れに沿って攻撃するより、「いや人間だよ」と考えたい。 そういうことと近いことを言っているのがドストエフスキーだと思うんですよ。「私はクリスチャンだけど、人間だから借金する、酒も飲む」とか。
――ただ、社会と個人を切り離して、主体の自由を強く出しすぎたら、今風に言うと「自己責任論」みたいなものにも結びついてくると思うんですが。
にゃるら:
じゃあ申し訳ないですけど自分はフリーランスでクリエイターとしてやってるんで、自己責任でしか生きたことがないです。そこにバイアスというか、偏重するのはしかたないんじゃないですかね。
――なるほど、社会的な構造の結果ではないと。
にゃるら:
いやもう、ずっと社会を憎んで生きてます。だってなんか、「会社に確認します」とか「預かって上長に確認します」とか何だよとか。「お前の意見は?」と、ずっと思いますもん。今もそれ本当に嫌いなんで。
――(笑)。いや、にゃるらさんのお話を聞いているとすごい一貫してますね。つまりにゃるらさんがテーマにしておられる実在主義というのは社会構造より、個人の自由を強調するわけですから。
にゃるら:
会社にいる限り自分の責任ってものを会社に預けるから。そこは自己責任じゃない人たちにムカつくことはかなりあるので。
――ただ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は、ある種のカウンセリングとしても見れる気がするんですが、それは間違いなんでしょうか?
にゃるら:
いやあ、『エヴァンゲリオン』をカウンセリングとして見る人がいるとかと同じ話じゃないですかね。 稲垣さんに「自分自身とその周辺のことを書いてるね」と指摘されたことがあるんですけど、自分自身とその周辺のことを13話分も書いたらそれは確かにカウンセリングですよ。だから僕のカウンセリングですね。
――なるほど。
にゃるら:
カルテに近いかもしれないですね。ものすごい鬱病だから、映画も2時間閉じこもれると楽なんですよ。そのことしか考えなくて済むんです。生きてると、後悔のことばっか思い出すから。
――そうしたにゃるらさんの「カルテ」とも言える物語が、アニメとして表現されます。13話を通して視聴者に何を感じ取ってほしいですか?
にゃるら:
僕は、超てんちゃんという、色々と病みながら進んでいく女の子がいて、それに対して「そんなものを描くな」というより、「その子を見てどう思いますか」というだけの話だと思っているんです。
「この子は少なくともここへ来たよ」というのが、全13話として描かれます。若者の暴力性や薬物依存はなぜ起きるのか。アニメではそれが尚更出ていると思いますが、僕としては「それを真剣に書いただけ」という、ただそれだけの気持ちがあります。
――ありがとうございました。
【取材後記】
取材中、表現の自由やゾーニングの是非を巡り、記者とにゃるら氏の間で意見が異なり、場に緊張が走る瞬間があった。一方でそれは作品に真摯に向き合っているからこそ生じた摩擦であり、この作品が持つ熱量そのものでもあると感じた。
冒頭で記した通り、記者は現代的な病理を浮き彫りにしている『NEEDY GIRL OVERDOSE』を傑作と考えている。にゃるら氏が中心的に手掛けた今回のアニメ版が、どのような現代の景色や空気、そして問題提起を見せてくれるのか。いち視聴者として楽しみに待ちたい。
なお、『NEEDY GIRL OVERDOSE』を巡っては現在、係争が存在することが公に知られている。今回の取材は、それらの問題には触れず、あくまでこれから世に出る「アニメ作品」を中心に取り上げて欲しいというにゃるら氏側の依頼のもと、筆者が合意し実施したものである(取材・執筆・構成:福山幸司)。



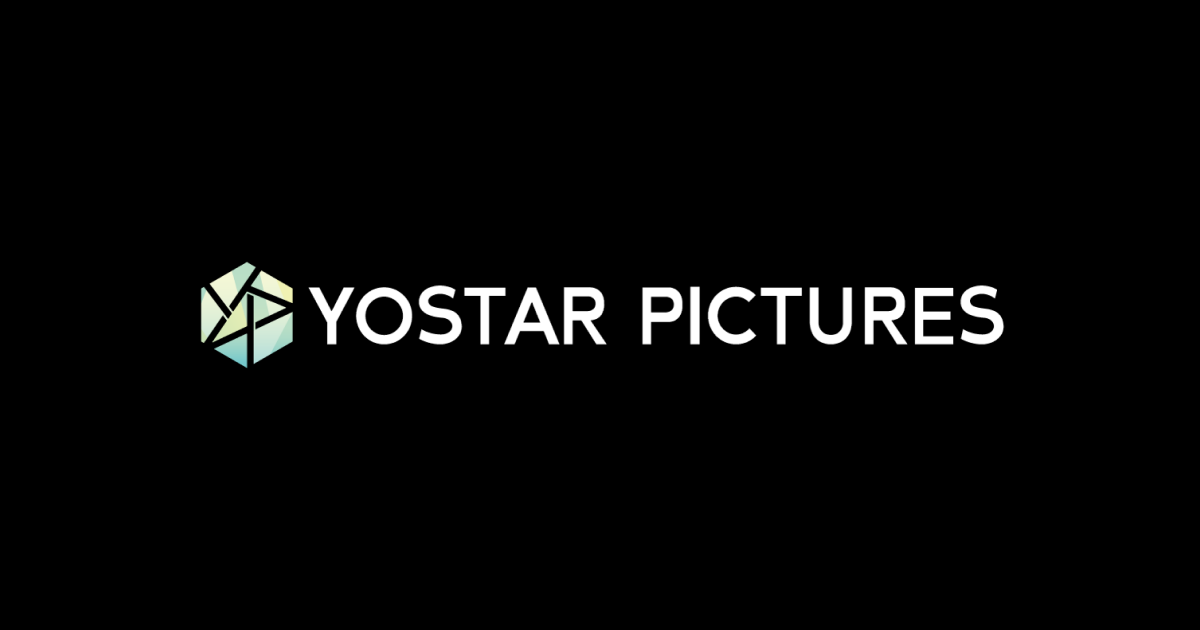

![[本]承認欲求女子図鑑 新装版](https://imagedelivery.net/QondspN4HIUvB_R16-ddAQ/5b6c1a2d5496ff4fa1000c49/63c5acd21cee487ea329.jpg/fit=scale-down,w=1200)

コメント (3)
コメントを残す